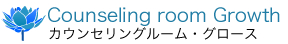コラム
コラム:かつてヤングケアラーだった人
コラム 2025/04/02 (水) 4:44 PM
かつてヤングケアラーだった人:はじめに 助け合うことが生きる目的のすべてではない
子育て、重度の障害や病気、介護、冠婚葬祭などの行為は、必ず人が人をケアする状況が生まれます。ケアという行為には、人と人とが関係を通じて助け合うことが避けて通れません。育て、育てられた、産んだ、産まれたという行為の能動と受動は、人間の関係そのものの原点ではないでしょうか。しかし、助け合うことが生きる目的のすべてであると思い込んでしまうと、そのケアそのものに問題が発生するかもしれません。
ケアとは、お互いの人間が仲良く融合しつづけることではなく、助け合った先に、必ず自己実現という将来の夢を各々がめざすことができる人間関係でなければ心の健康は害されるでしょう。
ひとりひとりの人間の自己実現の欲求をみた満たす可能性を奪わないことは、人々に生きる希望と強さを与えてくれるのではないでしょうか。
かつてヤングケアラーだった人:ヤングケアラーとは
親の病気や精神疾患などによって、本来は大人がやるべき家事や親のケアなどを必要以上にしなければならない家族システム内の子どもをヤングケアラーと呼びます。年齢は18歳未満とされています。
家事や介護、家計のための経済活動などに時間をあてがうために、遊びにも行けない、友だちのできず人間関係から孤立する、学業に集中できない、部活動にも参加きないなどの自己犠牲の日常は、不安で眠れないなどの問題を抱えます。そして、さらに問題なことは 、わが子にケアをさせることが、いつの間にか当然と思っている親や家族の存在です。
ケアされる側が支配的で社会性が乏しく閉鎖的で、ケアラ―である子どもを暴言や暴力で操作している場合、相談窓口や社会福祉資源と結びつくことが難しく、子どもにも複雑性PTSDなどの症状が現れる可能性は高くなります。
とくに、その親に毒親傾向が強かったり、過干渉、子への依存度が高かったりすると、子どもは親のケアをしなければ評価されない条件付きの環境で人の顔色を伺いながら生きることが正しいのだと刷り込まれてしまいます。
ヤングケアラーが成人した時に、子ども時代から当たり前のように続けて来た親や家族へのコーディネート(家族の調整役というケア)が原因で、自分のケアができず、他人の世話ばかりをする、自己評価が低く、疲労感やイライラ、ちょっとしたことに怒りを強く感じることが多ものの、自分は怒ったり、暴言を吐いてはいけないと、常に正しくよい人を演じる結果、本来の自分を見失ってしまうでしょう。
親との関係が支配的で、かつてヤングケアラーだった人は、いわゆるアダルトチルドレンの傾向が非常に高いといえるでしょう。
かつてヤングケアラーだった人:ヤングケアラ―の日常
・わたしは親に代わって兄弟の面倒を見ている
・わたしは親に代わって炊事、洗濯、掃除を引き受けている
・わたしは親に代わって祖父祖母の介護、トイレ、食事の見守りをしている
・わたしは第一言語が話せない親に代わって通訳をしている
・わたしは家計を支える為にアルバイトをして障害のある親に経済援助をしている
・わたしはアルコール、ギャンブルの問題を持つ親に対処して家族を維持している
ヤングケアラーは「~しなくちゃいけない」状況が必要以上に日常化しています。自分がしっかりしないと家族が生きてゆけないのではという緊張感と不安感は非常に大きく、自己実現や将来の夢は二の次か、あるいは感じないように萎縮させているかもしれません。そして、こうした生活状況で相談する場所や話し相手がいなかったとしたら、あまりにも過酷です。
ケアされる親が子どもに「あなたには感謝している、でも、自分の人生を見失わないように、あなたの楽しいこと、好きなこと、やってみたいことを真剣に考えて、その道をめざしてほしい」と自己実現の欲求が幸せへの入り口であることを心から伝えてあげれば、ケアすることも、自分の時間を作り楽しむことも共存しやすくなると思います。しかし、ヤングケアラーの一部の親にはこれをさせない原因や状況があります。
かつてヤングケアラーだった人:「自分のことが親のこと、親のことが自分」という曖昧な自我
親子関係の原点を見ますと、必ず親子間の愛着形成の問題が見えてきます。子どもは自分が成長するために生得的本能で親にすがり、アメリカの心理学者A.H.マズローが言うところの、欠乏欲求と呼ばれる生理的欲求、安全欲求、社会的欲求、承認欲求を満たそうとします。
こうした原点である親は、子どもにとって言わずもがな、とりわけ特別な存在です。どんなに酷い生活でも、どんなに自分自身の時間が奪われても、どんなに折檻されても、親が嘆いたり、悲しんだり、苦しむ姿を子どもは見たくありません。
ケアラ―である子どもは、親のためにそのケアを頑張り、自己を犠牲にしているでしょうが、本来は子どもの安全地帯である親の苦しむ顔が見たくないがために、自分の安心ために親を元気にしようと親のケアに奮闘ます。すると、この親子関係の主人公が曖昧になり、「自分のことが親のこと、親のことが自分のこと」という曖昧な自我が出来上がります。ゲシュタルト心理学のF.S.パールズ博士の言う「融合(confluence)」という心理的一体感が正常な生き方であると刷り込まれます。
どこからが自分でどこからが他人であるかがわからず、それ故に、他人の領域に干渉しすぎたり、自分が正しいと思っているから当然パートナーも正しいと思っているという思い込みによって、人間関係全般でトラブルを起こしやすくなります。
こうした人は、話し方も突飛で、それが言葉にしていない頭の中の空想であっても、相手にさもさっきまで話していたその話の続きのように、主語がなかったりと、聞き返して説明が必要な話し方をします。そして、自分と同一でないと不機嫌になり、他者の少しの差異も耐えられなくなります。
かつてヤングケアラーだった人:ケアする側とされる側の心理
ケアラ―と要介護者、要支援者との間に展開する感情には、常に罪悪感が往来しています。こうした罪悪感を持ち続けて感情の不安定な関係でいるよりも、
わたしのせいであの子に迷惑を掛けて、あの子の時間を奪っている。
自分がしっかりしないから、ひとり親の母に疲れた思いばかりをさせてしまう。
このような思いが、単なるやさしさの時もあれば、「もうできないよ!」という怒りを表明した後に、我に返って「ごめんね」と仲直りできる関係です。こうした感情をお互いが見せることができる信頼関係をもっていますと、頼れるところには頼るようになったり、自分らしくいられる時間を日常生活に取り込めたりできるようになるのですが、何度も何度もこうした罪悪感の往復を繰り返してお悩みの場合は、カウンセリングをおすすめします。
先ほどの「融合(confluence)」の話で説明しますと、この両者の往復する罪悪感は、自分と同一でないと不機嫌になり、他者の少しの差異も耐えられない心の反動として生まれているため、その家族システムに第三者が介入する必要が十分にあります。
かつてヤングケアラーだった人:ヤングケアラーの心の問題
ヤングケアラーのメンタルケアの問題は、ヤングケアラーに相談相手がいないことがネックとなります。閉ざされた家庭内で社会福祉資源やサービス、援助を有効に活用されないままか、あるいはその資源や援助が不十分であったために、過剰に我慢を続けなければならず、自己実現の欲求を見失ってしまうことです。
過去に自分の心をケアする機会すらなかったヤングケアラーが成人した場合、生きづらさや慢性的な疲労感、自己否定感、不快な場所への過剰適応などの問題を持っている場合は多いでしょう。ほんとうはつらいけど、自分が犠牲になってケアする生活が当たり前だと判断する、歪んだ認知が形成されているからです。
「みんなが安心すると私もやれやれと安心できる」
本来「やれやれ」は必要ありません。
私とみんなの安心は必ずしも一致はしないし、みんなとの安心に一喜一憂していたら、そのこと自体が生きる目的になってしまうことに気がつけません。
心理カウンセリングはこの認知を修正して、本来の私を感じられる作業をしています。自己の内省と記憶が整理されると、自己実現の欲求が高まりますが、過剰適応や自己否定感が強いと、自己実現の欲求を感じることに罪悪感(トラウマ)が湧いてきます。これも認知の歪みなので、「一体、誰があなたにその罪悪感(トラウマ)を感じさせているの?」という問題で自分自身を振り返ってもらいます。
やりたいこともできず、あるいはそれを感じないようにと封印し、我慢を強いられる環境で生きてきた人は、感じてはいけないタブーの感情である「怒り」が必ずあります。しかし、この怒りが自我を成長させ、自分自身が思ってもみなかった意外な自分の声を油性の太いマジックで書いたように聞かせてくれます。
「本当の私は○○がやってみたかった」という気づきの声です。
●ご興味のある方はこちらからご予約を頂けます。
【執筆者情報】
大塚 静子
資格
- 臨床心理士(NO:18162)
- FAP療法上級資格取得
所属学会
- 日本臨床心理学会
- 日本ブリーフサイコセラピー学会
- 国際トラウマティックストレス学会
(International Society for Traumatic Stress Studies)
経歴
- 2005年 アライアント国際大学/カリフォルニア臨床心理大学院 臨床心理学
修士課程卒業 - 2005年7月 アルコール依存症専門病院、周愛利田クリニックにて依存症治療に携わる。
- 2009年7月 アダルト・チルドレン第一人者の斎藤 学先生がやっておられるIFF・CIAP相談室勤務。家族臨床、トラウマ治療について研鑽を積む。
- 2014年7月 横浜にてカウンセリングルーム・グロース設立。
- 2015年4月 浦和大学 総合福祉学部 非常勤講師 「心理療法」,「精神保健学」担当
研究実績
研究実績はこちらをご参照下さい
著書
『甦る魂』はこちらをご参照下さい
トラックバックURL
https://shizuko-o.com/kanri/wp-trackback.php?p=8051