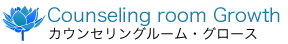PTSD(心的外傷後ストレス障害)の治療と心理カウンセリング
PTSD患者の特徴

・全く場違いな言葉や場面が頭の中に侵入してくる
・自暴自棄な判断をしてしまう
・時には幻聴や幻覚、幻臭を感じる
・突如、強烈な羞恥心が襲ってくる
・日常的でごく些細な音に対する驚愕反応を表す
「今この場所でどうしてそれが起きるの!?」
日常生活の中で健常者には理解しがたい侵入症状、例えば突然襲来する恐怖や怒り、恥ずかしさ、悲しさや憂うつなどが自分の意志に反して勝手に飛び込んできます。
警戒心が強い。 イライラしている 。確認癖。無表情。 茫然自失。 顔面蒼白 。突然泣き出す 。引きこもる。怒りっぽい 。自暴自棄。パニック発作 。過呼吸 。アルコールなどの依存症の傾向がある 。
今、みんなが楽しく集う場所で、突如包丁が飛び込んでくるシーンや飛行機が墜落するシーンが、あたかも現実のようにPTSD患者の頭の中でフラッシュバックしていると仮定します。
仲間は「どうしたの?様子が変よ」と声を掛けるかもしれません。今包丁が飛んでいたなどという恐怖体験を言語化できないのがPTSDの特徴です。こうしたフラッシュバックは心の無意識の中から現われますから、心理カウンセラーとの共同作業なしに無意識を言葉にする作業は非常に難しいからです。
頭の中に不穏なフラッシュバックが襲ってきても、これは現実には起きないし、今、ここにいる私は、カフェで休息を楽しんでいるという判断ができるようになると、PTSD症状は回復に向かいます。それには自分の無意識に気づきを与え、自分に嫌がらせばかりする孤独感に支配されない環境に自分を置くことが大切です。
こうした深い孤独感の中で突如現れる恐怖を鎮静化し、リラックスした自分を感じながら健康な精神状態に回復させる役割を心理カウンセリングは担っております。
では、SNSや巷でも頻繁に耳にするようになったPTSD(Post Traumatic Stress Disorder:心的外傷後ストレス障害)についてご説明します。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)とは
PTSD(心的外傷後ストレス)とは、無力を感じるほど突発的で回避できなかった恐怖体験によって心に傷を負い、安全や安心感を脅かされる精神疾患です。
例えば、生死に関わるような身の危険に遭ったり、他者が死傷を負うような場面を目撃した時の恐怖が、フラッシュバックして何度も繰り返し頭に侵入しては日常生活を脅かす精神疾患です。
人の心は、想定外の衝撃的な恐怖体験に巻き込まれると、心の土台であった安全基地がその機能を失います。信じていたものが信じられなくなると人は不安になり、日常生活の時間軸が狂わされます。
過去-現在-未来という時間軸を持っていない人はいません。 現在の中の私は、願いや希望を思い描く「未来」と、体験から学習し記憶する「過去」によって「現在」を判断しながら生きています。ところがPTSDの場合、過去の記憶が現在の邪魔するために未来を想像しにくいストレスフルな人生を強いられます。言い換えますとPTSDとは、記憶によって健康な想像力がダメージを受ける精神疾患と言うこともできます。
PTSDの有病率
世界保健機関(WHO)の世界保険調査のデータ(日本版)によれば、日本で一生のうちに生死に関わるトラウマ体験をする率は約 60%と報告されています。
その中でPTSD の生涯有病率は 1.3%と言われています。この数字はパニック障害の障害有病率1.0%を超えています。
このようにのように、PTSDは身近な精神疾患として、より多くの支援や治療の受けやすい環境整備を必要としています。
PTSDが発症するまで
PTSDの発症期間は、非常に個人差があり、外傷体験の種類によっても異なります。
外傷の直後に症状が表れたり、外傷後の数日から数ヶ月後に発症することもあります。 PTSDは自然治癒することも多く、その割合は6~7割と言われています。
トラウマ体験直後にPTSDと同じ症状を発症しても、その症状が1ヶ月以内に治まった場合、診断名は 「急性ストレス障害」となります。1ヶ月が過ぎても症状が続いている場合、その診断名はPTSDとなります。
トラウマ体験後からその症状の持続期間によって、PTSDは以下のように分類されます。
・急性PTSD:症状が1〜3ヶ月の間持続します。
・慢性PTSD:症状が3ヶ月以上の間持続します。ストレス因子の暴露後、6ヶ月を超えている
・発症遅延型PTSD:外傷体験から6か月を過ぎてからようやく発症するPTSD
PTSDの発症原因
恐怖体験がPTSDの発症原因なのですが、その恐怖体験とはどのような性質を持っているのでしょうか。
・人への相談がしづらい
・自分に無力感を感じる
・突発的で回避できない
・予想外の出来事
これらの要素をいくつかもった恐怖に遭遇する、あるいは他者のこうした恐怖を目撃することでPTSDを発症します。具体的には以下に挙げられます。
・自然災害
地震、津波、火事など
・交通事故
加害者と被害者共にPTSDを発症
・暴力
ケンカ、ハラスメント、強盗、テロ、暴動、戦争、イジメ、性暴力
・対象喪失
ペットや親しい人との死別や身体の欠損
多くの人は、こうした負のイベントに巻き込まれるはずはないと思いながら日常生活を送っています。たとえあったとしても上手にそのトラブルを回避できるという自己効力感や自己愛を適度にもって安心感を土台に生活しています。
それが突如、回避できない災害や事故、事件に巻き込まれたとしたら、恐怖や不安を感じない人はいないでしょう。当然、今までの安心感が信用できなくなります。
PTSDの診断基準
PTSDは、DSM-5(精神疾患の分類と診断の手引き)の第7章の「心的外傷およびストレス因関連障害群」に記述されて以下の診断基準は概要です。
A.危うく死にかねない、重傷を負う体験をする、または目撃している
B.心的外傷の出来事の後、侵入症状が存在し、反復している
C.心的外傷の出来事に関連した刺激を回避する
E.心的外傷の出来事に関連した認知と気分が陰性に変化している
F.心的外傷の出来事の後、過覚醒していしている、または反応性の著しい変化
F.B,C,DおよびEが、1か月以上持続する
1か月以上、トラウマに苦しめられて、日常生活に支障がある場合、PTSDと診断されますが 1か月以内でこれらの症状が治まった場合は、急性ストレス障害(Acute Stress Disorder)と診断されます。
PTSDの特徴的な症状
以下の3つの特徴的症状は 『心的外傷と回復』の著者ジュディス・L.ハーマン博士(Judith Lewis Herman)の『心的外傷と回復』(みすず書房)の第2章の「恐怖」の中で、PTSDによる3つの反応として記述されています。J.L.ハーマン氏の3つのカテゴリーは、その後、DSM-5の診断基準となります。その3つを比較してみました。
1-1. 再体験 (DSM-5)
突如、今起きているかのようにトラウマ体験がフラッシュバックする。睡眠時に悪夢となって反復もします。DSM-5ではBが当てはまります。
1-2. 侵入(Instrusion)
(J.L.ハーマン博士)
心的外傷を受けた刹那の消せない刻印を反映します。反復再体験を特徴として、時間は外傷の時の瞬間に停止します。覚醒時はフラッシュバック、睡眠時は悪夢が頻発します。
悪夢もフラッシュバックも物語性を欠き、言語化できず、前後関係もありません。 この点が幼児期の記憶の物語性を欠く映像的(イコニック)で感覚的な記憶と似ていることを、アメリカ精神科医Van Der Kolk氏は指摘され、PTSDによって交感神経が活性化すると言語記銘力が低下した記憶となり、中枢神経系で幼少期の感覚的で映像的な形式に戻ってしまうのではないかと述べています。
ここにトラウマ記憶の言語化の難しさの問題が述べられています。
2-1. 狭窄(回避) (DSM-5)
トラウマ体験を呼び起こす記憶、思考、状況、人、を避ける。
トラウマ関連の人、場所、会話、行動、物、状況を回避します。 DSM-5ではCが当てはまります。
2-2. 狭窄(costriction)
(J.L.ハーマン博士)
屈服による無感覚反応の反映。 DMS-5(精神疾患の分類と診断の手引き)の中では「回避(Avoidance)」と記載されています。
M.セリングマンの学習性無力性にも似たこの症状は、無力感といかなる抵抗もできないと知ったときに、最後の防衛として意識を凍結した降伏状態であるとJ・ハーマン氏は述べています。
また、狭窄症状は「未来を予測することや将来の計画を立てることを邪魔する」(同著 P68 11行目)とも述べています。
消せない刻印を意識に反復する「狭窄」と意識を凍結した「侵入」は、「記憶喪失と外傷そのものの再体験」(同著 P69 6~7行目)を往復しながら予測できない世界に投げ込まれ、相矛盾しながら、孤立した感覚を強めてゆくと述べています。
3-1. 過覚醒 (DSM-5)
無謀または自己破壊的な行動をする。過度の警戒心がある。過剰な驚愕反応を示す。集中困難である。入眠維持ができない、または眠りが浅いなどの睡眠障害が継続します。
DSM-5ではEが当てはまります。
3-2. 過覚醒
(hyperarousal)(J.L.ハーマン博士)
トラウマによって長期間の緊張した防衛体制が働きます。持続的な警戒態勢が日常化します。集中困難や驚愕、睡眠障害が伴います。
「正常人が持っている、警戒しながらリラックスもしているというレベルの注意の「基準線」がない」(『心的外傷と回復』P.51 9~10行目)と述べています。 トラウマ体験の恐怖は、慣れの欠如によって、絶えず覚醒しなければなりません。
・その他の症状
「離人症」
自分自身を傍観者のように感じる症状(夢の中のような、時間の進みが襲い、体に現実感がない。
「現実感喪失」
世界がぼんやりして歪んでいる
PTSDの併存する精神疾患
PTSDと治療
・安全性と安心感
「この状況の中のわたしであれば、安心感は以前より大きい」をイメージできますか。
PTSD患者にとって、安心感と安全性が何よりの薬となります。その場所であれば、恐怖や不安、悲しみ、羞恥心、怒りを感じても、私は乗り越えてゆけると思えるような環境整備は非常に重要です。
特に、ストーカー被害者や性暴力などの人間関係そのものがトラウマである場合は、 福祉関連の社会資源(ネット上の被害者相談機関や地域のサービス、リモート面談など)を活用したり、SSRI(抗うつ薬)や抗不安薬を服用しながら、「この状況の中のわたしであれば、安心感は以前より大きい」と思える環境づくりをすることで、PTSDによって失われた現実感が徐々に回復するでしょう。
PTSDに効果のある昨今の心理療法も、こうした安心安全な環境整備を含めたかたちのものが多くなっています。
以下にあげる習慣を日常のルーティーンとすることで、PTSD症状を和らげる効果があります。
・リラクゼーション
日常生活内にルーティン化させて、心の安定を保持することは、PTSD改善に効果を発揮します。マインドフルネスなどの瞑想の時間を設けて、ひとまず過去を切り離し、常識や一般論を心から追い出してみます。
そして、今現在の自分の状態を見つめる時間を感じてみる習慣を作りましょう。また、短時間でも構わないので それが私にとって心地よいと思える無理のない身体のストレッチも、自律神経を整え、安心感を大きくしてくれます。
・食事療法
その代わりに、自律神経を興奮させるカフェインや感情を麻痺させるグルテン(小麦粉など)を避ける食事療法も心の健康と安定には非常に重要です。
「健康」という言葉に対して、「自分は健康でなくてもいいんだ」という自己否定の声が聞こえてくると食事療法は、無理な荒行になってしまいます。
その自己否定の声は本当にあなたの声かどうか、誰かに言わされてはいないかを心理カウンセリングで確認してみてください。
・その他
人間は守られていると感じるだけで心地よい感覚を感じることができます。 自分の味方になってくれる物や人を集めることも効果があります。
お守りやおまじないも、PTSDの場合は非常に大切です。安心感を探しながら傷ついた心を修復する作業が、後年、あなたの精神的回復力(レジリエンス)を育てます。
そして逆境を乗り越えてトラウマサバイバーとなった自分の力に必ず感動するでしょう。
PTSDに有効な薬物療法
PTSDの治療には、患者と治療者との間に深い信頼関係がなければ、様々な心理療法も効果を発揮できません。しかし、患者は衝撃的なトラウマ体験によって人間不信が強かったり、情緒不安定だったり、外出できなかったりで、日常生活への安心感を失っています。
その補助として薬物療法は非常に効果的です。 PTSDの治療薬は、神経伝達物質のセロトニンの分泌を調整して心を安定させます。
SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)は、副作用もなくPTSDの治療に用いられている薬です。SSRIの薬剤名は、パキシル・レクサプロ・デプロメール・ルボックス・ジェイゾロフトなどです。 薬物療法は心理療法にくらべて非常に早く効果を発揮します。
日常生活も安定させてくれます。しかし、薬物に依存してしまうケースは非常に多いので、自分の心の問題に気づきを与えて薬に頼り過ぎないことが、良い人生を送るためにも非常に大切です。
そこで欠かせないのが心理療法です。PTSD治療に有効な心理療法は以下のとおりです。
PTSDに有効な心理療法
・持続エクスポージャー療法 (Prolonged exposure therapy)
持続エクスポージャー療法は、PTSDの治療に有効な行動療法のひとつで、トラウマ体験の不快な記憶に介入する治療法です。
トラウマが本来危険でない場所でも危険と認知していることに気づける心理療法です。患者の恐怖そのものに迫るため、心理療法家との信頼関係と安心感が構築されていないと、逆効果となる場合もあります。
面接は一回90分から120分間で行います。1週間に1回から2回のペースで合計10回の面接が行うのが一般です。
・EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing :眼球運動による脱感作と再処理法)
EMDRは、治療者が患者を前にして、左右に指を振り、その動きを目で追いかけ恐怖体験のトラウマを脱感作させる心理療法です。EMDRは90年代前半にアメリカから日本に広まった新しい心理療法です。
この眼球運動によって、外傷体験に対する脳の情報処理プロセスが促進すると、恐怖を減少させる効果が生まれます。パニック障害や強迫性障害、諸々の恐怖症にも有効と言われています。
・トラウマ・フォーカスト認知行動療法
(TF-CBT:Trauma focused cognitive behavioral therapy)
TF-CBT は、当初、トラウマ体験やPTSDを発症した子どもを対象に開発された心理療法ですが、現在は大人にも適用されています。
1段階目の「安定化」は、子どもと安全な保護者の両方に心理教育をした上で、トラウマを思い出す訓練をします。
2段階目の「トラウマ体験の語りと処理」では、トラウマをより具体的に細かく処理できるように対話型で進行します。
3段階目の「統合と強化」では、トラウマの恐怖に立ち向かうための階層表を作成しつつ、TF-CBTのスキルやリラクゼーショを習得してゆくプログラムとなっています。
研究者によるとTF-CBTは、小児期のPTSDの治療に有効で、複雑性PTSDの治療にも現在、応用されています。
今まで挙げた心理療法には、トラウマの恐怖体験を必ず思い出す苦しい作業が伴いますが、FAP療法は、トラウマを無理に思い出ださないまま、不快な記憶を統合する画期的な心理療法です。
人は人との共感を経験すると、なぜか共感後に心がスッキリします。治療者とPTSD患者との間に起きた共感は、脳内の神経伝達物質ミラーニューロンの作用と言われています。
ミラーニューロンの共感反応がPTSD患者のトラウマを治療者へと転送されることで、PTSD患者はトラウマから徐々に解放されます。
PTSDを抱える方にとっての安心・安全の問題と「杞憂」の話
中国の週の時代にある男がいて、天地が崩壊して住む場所を失うことにとひどく心配していました。
この男は心配性のあまり食欲を失い不眠症になってしまいましたという中国の『列子(天瑞)』の故事に由来する「杞憂」の話は、正しくPTSD患者の不安や脅威をよく物語っていますが、PTSD患者と異なるところは、相手に自分の心配や恐怖を抵抗なく語れるかどうかという部分です。
たとえ語っていたとしても、自分の本当の気持ちに深い罪悪感と恐怖を、加害者や事故、事件から与えられているために、本当の気持ちを易々と語れないのがPTSD患者の問題点であり、治療に時間を要する原因となっています。 トラウマ記憶の言語化の難しさもそこに伴います。
FAP療法は、言語化を無意識に回避するトラウマ記憶を無理に暴露したり、言語化したりせずに治療が進行するため、トラウマ治療にとても優れています。
PTSDを発症しづらい人生を送るために自分を信じる力を持つ
・感受性が強くHSPである
・発達障害がある
・アドレナリン分泌が多いスポーツマン
・幼少期の虐待トラウマ等の逆境体験
・男性よりも女性
・月経前症候群(PMS)がある
・カフェインを多く摂取する
こうした性格傾向やタイプは、養育者との愛着形成期に虐待やネグレクトなどのトラウマを日常的に反復していたことで、PTSDに罹患しやすい性格形成がなされているかもしれません。
また、家庭環境での虐待などによって、すでにPTSDが日常化している複雑性PTSDや愛着障害、アダルトチルドレンなどの問題を含んでいることが多く、家族システムの内の人間関係に巻き込まれない自分を育てることが必要でしょう。
自分のやさしさから対人関係のトラブルに巻き込まれ、トラブルの相手の○○さんという名前を聴いたり見たりすると動悸とパニック発作を1か月以上発症した患者は、幼少期より家族の中で常に自分がやさしく立ち回り、両親の不和(両親のケンカのトラウマ)が再び起きないように頑張って来たことが本当の原因でした。
・その事故も事件もトラブルも私のせいではない
・私が安全にかつ安心した生活をして何が悪いのだろうか
・いとも簡単に安心感と安全を奪う本当の原因にわたしは気づいているだろうか
こうしたレジリエンス(精神的回復力)が持てる認知によって、強固な自己肯定感を心の土台にしながら本当の原因に自分が気づくことで、その後、PTSD症状の発症を予防できる力になるでしょう。
心とかからだの安全を確保するには
「たとえあの恐ろしい記憶がフラッシュバックしても、今の私は安全だから安心してもかまわない」
自己肯定的な認知で自分を観察でき出すと、PTSDの治療は終盤に向かいます。
悪い記憶がフラッシュバックしても、それが見下ろせるくらい小さいものに感じると心は健康に向かいます。そのためには安全な場所と信頼できる聴き手が不可欠です。
人間関係のトラブル(性被害やパワハラなど)や事件、事故の被害及び目撃ででPTSDを発症し、引きこもりで人間回避せざるを得ない場合は、オンラインカウンセリングなどを活用して、安全を確保しながら自分の安心感を育ててゆきましょう。
カウンセリングのお申込み
【執筆者情報】
大塚 静子
資格
- 臨床心理士(NO:18162)
- FAP療法上級資格取得
所属学会
- 日本臨床心理学会
- 日本ブリーフサイコセラピー学会
- 国際トラウマティックストレス学会
(International Society for Traumatic Stress Studies)
経歴
- 2005年 アライアント国際大学/カリフォルニア臨床心理大学院 臨床心理学
修士課程卒業 - 2005年7月 アルコール依存症専門病院、周愛利田クリニックにて依存症治療に携わる。
- 2009年7月 アダルト・チルドレン第一人者の斎藤 学先生がやっておられるIFF・CIAP相談室勤務。家族臨床、トラウマ治療について研鑽を積む。
- 2014年7月 横浜にてカウンセリングルーム・グロース設立。
- 2015年4月 浦和大学 総合福祉学部 非常勤講師 「心理療法」,「精神保健学」担当
研究実績
研究実績はこちらをご参照下さい
著書
『甦る魂』はこちらをご参照下さい