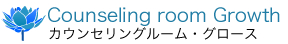コラム
コラム:産後うつ病
コラム 2025/03/20 (木) 4:40 PM
産後うつ病( postpartum depression, PPD)とは
懐妊から出産までの間、おかあさんは赤ちゃんを守りまもりながら成長させます。また、母体の周辺にいる人たち(家族、親類、医師、看護師その他)は、おかあさんを見守りながら、出産の不安を軽減する役割を担います。
しかし、夫婦間のトラブルや社会経済的な問題、望まない妊娠などでこの役割やバランスが崩れると、女性は不安やストレスがたかま高まると同時に、精神疾患を発症する割合も高まるでしょう。無理もありません。分娩後の母体の身体的変化は急激で、ホルモンバランスは乱れ、情緒不安定な状態を作りやすいからです。
けれども、こうした環境因と身体因によって発症する「産後うつ」を予測することは必ずできますから、あらかじめの予防策をご夫婦で話し合うことが大切です。
産後うつ病( postpartum depression, PPD):産後うつを予防するには
産後うつを回避するために、あるいは産後うつから回復するために、夫婦間の心理面でのケアや前もっての予防は、その後の家族に心の健康と安心感を与えてくれます。
ご夫婦がストレスフルな生活に翻弄されることなく、お互いがいがみ合いや怒ることをやめた時、あるいはそれを食い止めることができたとき、あるいはまた、仲直りできる素直さを表現できた時、きっとその家族は流行に脅かされることなく、かけがえのない美しいものに出逢います。そして妻を夫を我が子を「尊い」と感じる筈です。
こうした関係を基盤に置けば、ゆるぎない安心と喜びを獲得することができると、誰もが気がついているのに、的外れな方向に自分の感情が流されてしまうのはなぜでしょうか。
マタニティブルーが長引いて、産後うつにならないためにも、夫婦間の心理システムを事前に観察することを心理カウンセリングは推奨します。
産後うつ病:症状
産後うつとは、出産後1か月以内に発症する大うつ病と言われています。赤ちゃんへの関心がない、食欲がない、慢性的な疲労感やイライラ、無気力、体の痛みを感じたりします。
出産後の母体と生殖器の変化はすさまじく、分娩後には子宮に子どもを宿していなかった妊娠前の状態に体は戻ろうとします。いわゆる、産褥期(さんじょくき)と呼ばれる時期で、6~8週間かけて妊娠前の状態に体は戻ろうとします。
産後うつ:その割合
日本産婦人科医会のデータによれば、産後うつを発症する女性の割合は、10~15%の罹患率があると報告されています。
産後うつは、産後3か月以内に発症する場合が多いと言われています。マタニティブルーの場合ですと、およそ1週間から2週間程度で回復するのですが、産後うつの症状は2週間以上持続します。マタニティブルーがあった女性は、産後うつ病発症のリスクが高まると言われています。
産後うつの発症の原因
(身体的原因)
①産褥期の身体的変化にともな伴うエストロゲン、プロゲステロンの減少
②難産であった。出産の際、出血が多かった場合も産後うつ発症原因になると言われています。
(精神的原因)
過去に何らかの精神疾患やうつ病の既往歴がある。
(環境的原因)
・夫も妻も実家が遠く、パートナーや親類からの援助がない。母体と赤ちゃんのための相談所や地域ケアシステムのサービスを活用していいない。パートナーの仕事のストレスが高く、サポートなど頼めないと勝手に思い込んでいる。
・医療機関では産後検診を受けることになっています。助産師さんのアドバイスで産後うつの予防につながります。それにもかかわらず、そのアドバイスを受け入れない、あるいは産後検診を受けない。こうした心理状態は孤立を招きます。孤立を招く方向にわざわざ招いている自分がいる場合は、システムのカラクリを疑いましょう。つまり、
産後検診へ行かない⇒夫が呆れる⇒産後うつがひどい⇒実家が介入する⇒実家にいた頃の自分を親はいつまでも私に求める⇒夫がこれに呆れて離婚と切り出す⇒離婚で私が実家にもどり、親は元もシステム+孫が側にいることで万々歳!
娘を心配しながら、親が自分の願望を無意識に実現させる典型です。夏目漱石の小説に出てきそうなエゴイズムへの無知が招くシステムの恐ろしさです。
気の毒なのは、娘(妻)も夫もお互いの実像を知り合い、理解し合うことなく離婚してしまったことと、人間関係の間であっちへこっちへ振り回される赤ちゃんでしょうか。
産後うつ:産後うつの診断基準
以下の状態がほぼ毎日続き、5つ以上の症状が2週間以上続くことで「産後うつ」と診断されます。
・涙を流す、空虚感、絶望などの抑うつ気分
・体重の減少または増加(例:1か月で体重の5%以上の変化)
・興味または喜びの著しい減少
・不眠または過眠
・焦燥感と制止(落ち着きがない、のろくなる)
・思考、集中の困難
・無価値、過剰な罪悪感
・死についての反復思考(自殺念慮、自殺企図)
産後うつ用のスクリーニングとして「エジンバラ産後うつ病質問票例えばエジンバラ産後うつ病スケール(Edinburgh Postnatal Depression Scale)」があります。質問票は10項目で構成される自記式質問票です。スコア合計9点以上で陽性と判定されます。その後の診断を精神科医が引き継ぎます。また、産後うつに似ている病気で出産後に罹患しやすい病気が甲状腺と脳下垂体機能の異常です。これらも集中困難や不安感、、体重の増減が見られます。誤診のないよう、血液検査やCT検査を行う場合もあります。
産後うつ:子育てへの願い
「明るく、のびのびと、見守られながら、みんなと仲良く、健康に、わが子は育ってほしい」
お子さんをお持ちの親であれば、わが子に上のような願いを心の中に持っているのは、ごく当たり前のことだと思われていることが多いのではないでしょうか。
「お母さんと赤ちゃん」というイメージには、やわらかさ、あたたかさ、ぬくもり、あんしんかん、へいわ、いっしょ、あまえ、などのことばが、ひらがなで浮かんでは来ないでしょうか。
けれども、お母さんに安心とゆとりの環境が整備されていないと、これらひらがなのイメージが重圧にしかならず、ヤワラカサ、ヌクモリ、アンシンカン、ヘイワ、イッショ、アマエとなってしまいます。
しかし、どういう訳か、お母さんたちのガルガル期は長引いて、夫やお子さんにイライラと怒り、不安と抑うつを表現してしまいます。無理もありません。「私は毒親の入り口をノックしてしまったの!?」と不安になるのも当然です。
また、育児という新しい環境が、「正しい子育て」や「親はこうあるべき」という正さ中心の判断によって、間違っていないか、自分の子育てはこれでいいのかという不安感や自責感、罪悪感を覚える場面が心の中に増えますので、心理的なストレスをさらに高めてしまうでしょう。
産後うつ病:「我慢しない」、「協力する」、「抱え込まない」がむずかしい
お母さんには「我慢しない」、「協力する」、「抱え込まない」という環境を自ら選択してゆけるようになる心理的なサポートが欠かせません。言い換えますと、「我慢させる」、「夫婦で争う」、「抱え込む」をあなたにさせてしまう心理的な原因は何か、「私はどうして相談ができないの?」「どうして抱え込むの?」「どうして我慢が多いの?」と自分への問いをしっかりと感じて考えてみることが、産後うつ予防に一番必要なことではないでしょうか。
ここで注意したいことがあります。それは
・どうして抱え込むの?
・どうして我慢するの?
・どうして子育てで夫婦間で争うの?
と尋ねてみても、何も答えが見つからないことです。それどころか「私がそんなことしてるの?」という疑問や被害妄想の方が上の3つの問いよりも優先してしまうことです。そして、たとえその答えが見つかったとしても、相手を責めることばかりに終始してしまいます。すると再びケンカや対立を繰り返す悪循環が繰り返されます。
こうして、変わらない私は延長されてゆきます(誰かがそうなるあなたを望んでいます)。
・問:どうやって抱え込むの?
・答:本当の気持ちを相手に伝えないと抱え込むの
(実は人間みんなが怒っているように感じて怖いの)
・問:どうやって我慢するの?
・答:昔からやってきたから我慢には慣れてるの
(それを思い出せなくすれば何でも平気)
・問:どうやって子育てのことで夫婦で争うの?
・答:なつかしい、わたしの親もやってたなぁ~
(暴力のあとはいつも仲良くなるから間違ってない)
自分の愛着を形成した養育者との過去の環境が、意識化されて言語化することができたとしたら、このように答えるかもしれません。( )内は、家庭内がすさまじく劣悪な環境であったにも関わらず、何とか生き残らなければと過剰適応してきた心の声です。
トラウマ体験が原因であなたの認知が歪んでいたことを、結婚や出産を契機にうつ病や夫婦間のトラブルで予想外の負の感情が露見した時にそれを表に出してはいけない、以前のように戻って!という願望で意識はその感情を抑圧しようとします。負の時間はそれでもあなたのいうことを聞きません。
「夫も仕事で疲れている。手伝え!なんて夫には言えない。」けれども「私ばかりが損をしているような気がする。
産後うつ:人に頼める。人に任せる。人にお願いをする。そして私は楽しむ
人にお願い事をしている自分を想像しましょう。
人に仕事や家事をまかせて、「自分は楽だぁ」と感じている自分を想像してみましょう。
自分一人では無理だから、頼れる人やサービスを探す自分を想像しましょう。
自分が選んだパートナーには、辛い仕事でストレスを溜めずに、ほんとうは楽になってほしいという自分の気持ちを伝えて、それをめざしましょう。
これらを想像した時、不安でしょうか、安心でしょうか。
この3つが自分に素直にできると、いともたやすく楽しい私はやってきます。そのお母さんを見て育つ赤ちゃんは、お母さんから楽しさのシャワーをあびるでしょう。
多くは過去のトラウマ体験が人間関係をぎこちなくさせ、頑張らせ、気づかいばかりに齷齪し、怖がり、本心を隠して生きることをあなたに強要します。産後うつの予防のためのも、当室でご自身を観察して家族と私の健康を育ててゆきましょう。
●ご興味のある方はこちらからご予約を頂けます。
【執筆者情報】
大塚 静子
資格
- 臨床心理士(NO:18162)
- FAP療法上級資格取得
所属学会
- 日本臨床心理学会
- 日本ブリーフサイコセラピー学会
- 国際トラウマティックストレス学会
(International Society for Traumatic Stress Studies)
経歴
- 2005年 アライアント国際大学/カリフォルニア臨床心理大学院 臨床心理学
修士課程卒業 - 2005年7月 アルコール依存症専門病院、周愛利田クリニックにて依存症治療に携わる。
- 2009年7月 アダルト・チルドレン第一人者の斎藤 学先生がやっておられるIFF・CIAP相談室勤務。家族臨床、トラウマ治療について研鑽を積む。
- 2014年7月 横浜にてカウンセリングルーム・グロース設立。
- 2015年4月 浦和大学 総合福祉学部 非常勤講師 「心理療法」,「精神保健学」担当
研究実績
研究実績はこちらをご参照下さい
著書
『甦る魂』はこちらをご参照下さい
トラックバックURL
https://shizuko-o.com/kanri/wp-trackback.php?p=8019