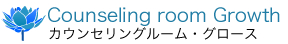アダルトチルドレン
アダルトチルドレンと複雑性PTSD
アダルトチルドレン 2021/10/09 (土) 4:12 PM

アダルトチルドレンについて考える時、同時に複雑性PTSDの問題は切っても切れない関係だなと実感します。
複雑性PTSDの問題は、PTSDの3つの症状(回避、過覚醒、再体験)の問題に加え、自尊心の問題、人への不信感、感情のコントロールの3つの問題とされています。
つまりPTSDの3つ症状に加え、その人の性格傾向の部分にまで影響を及ぼしているというのが、複雑性PTSDの特徴だと言えるでしょう。
つまり複雑性PTSDは「生きる」こと自体に長期に及ぼすトラウマの問題と言えるのです。ですのでそこからの回復という場合、それまでの役割をやめて行くという感じかも知れません。
アダルトチルドレンの場合、以下のような役割があります。
このように「本来の”私”」では無い「役割」で、大人になっても生き続けるというのが、幼少期からのトラウマを抱えたアダルトチルドレンの方々の特徴だと言えます。
・ヒーロー(英雄)
・スケープゴート(生贄)
・ロスト・ワン(いない子)
・マスコット、クラン(道化師)
・イネイブラー(支え手)
実際にトラウマの問題はトラウマを再演する特徴もありますので、大人になって原家族から独立し家族を持った際も「本来の”私”」が求めていない「役割」の中で、語弊がありますが「演じながら生きる」という展開が起こってくるのです。
お互いがお互いをリスペクトできない苦しい関係の中で離れられない関係。そんな「役割」というモノが、トラウマを抱えてしまているが故に出来上がってしまうのです。
当相談室では、その人が生きる上でのベースとなっている幼少期のトラウマについて、FAP療法を用いトラウマ治療をご提案させて頂きます。そうする事で、それまでの生き方の「癖」や「役割」から外れて自由に生きて行く事ができるのです。
例えば「イネイブラー」としての生き方の癖がついてしまっている場合、根底に母親との葛藤などを抱えている場合等があります。両親との葛藤がある家族の中で、依存的な母親を支える「いい子」として育って来ている場合、「母親を支えるいい子」として役割が認められている「イネイブラー(支え手)」としての生き方の癖がついてしまう場合があります。
母親を支えるけれど愛情は決して返ってこ来ない。母親はいざという時には守ってくれない。そんな関係性の中で幼少期を経てきますと、大人になった際に問題を抱えている人を支える事にとらわれてしまう事があるかも知れません。
”私”の自由を削って捧げても何も返ってこない関係性を繰り返す事で、自尊心が傷ついてしまうのです。そのような感じで、大人になってからの「役割」の問題について、家族を背景としたトラウマの問題にフォーカスを当てて対応を致します。
そうする事で「役割」ではなく、「本来の”私”」が求めている生き方を模索して行く事が出来るのです。そして心から満たされる生き方をして行く事ができるのです。
●ご興味のある方はこちらからご予約を頂けます。
【執筆者情報】
大塚 静子
資格
- 臨床心理士(NO:18162)
- FAP療法上級資格取得
所属学会
- 日本臨床心理学会
- 日本ブリーフサイコセラピー学会
- 国際トラウマティックストレス学会
(International Society for Traumatic Stress Studies)
経歴
- 2005年 アライアント国際大学/カリフォルニア臨床心理大学院 臨床心理学
修士課程卒業 - 2005年7月 アルコール依存症専門病院、周愛利田クリニックにて依存症治療に携わる。
- 2009年7月 アダルト・チルドレン第一人者の斎藤 学先生がやっておられるIFF・CIAP相談室勤務。家族臨床、トラウマ治療について研鑽を積む。
- 2014年7月 横浜にてカウンセリングルーム・グロース設立。
- 2015年4月 浦和大学 総合福祉学部 非常勤講師 「心理療法」,「精神保健学」担当
研究実績
研究実績はこちらをご参照下さい
著書
『甦る魂』はこちらをご参照下さい
トラックバックURL
https://shizuko-o.com/kanri/wp-trackback.php?p=3321